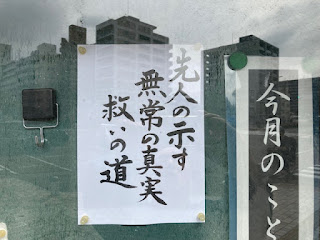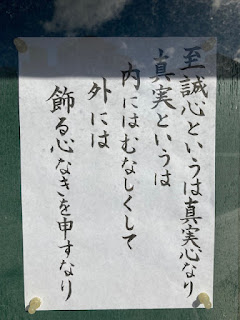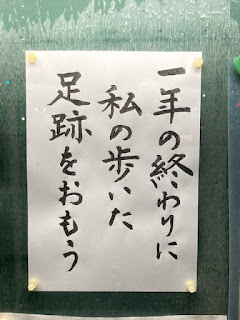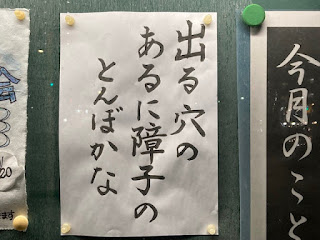4月のことば
.jpg)
「私は過去にではなく 今日と明日に生きる(エジソン)」 今年の桜はいつもよりだいぶ早く咲き、あっという間に過ぎ去ってしまいました。そのため、辛うじて毎年“ノルマ”にしているお向かいの徳泉寺さんの枝垂れ桜と私がジャンボ桜と呼んでいる『銀杏町の一本桜』は眺めることが出来ましたが、残念ながら大河原町の「一目千本桜」は今年も目にすることが出来ませんでした。 咲くのが早ければ、散るのも早かった今年の桜。あまりの早さに、散った花びらの掃除が追い付かないほど。時間をかけて綺麗にした場所も他の場所を掃除している間に見事に元通り。もうここまで来ると怒りどころかイライラも消え去り、諦めて笑うしかなくなります。 桜の花が咲くこと、そして散ることも自然なことなのに、私の都合で一喜一憂していることに気付かされました。 お釈迦様は 「世の中は行為(業)によって転変し、人々の行為によって転変する。(スッタニパータ)『ブッダ100の言葉 佐々木閑訳』」と仰っています。 4 月は新たなスタートの月。 何かと時間に追いかけられたり、気の疲れから失敗などをすることもあるでしょう。でも、その失敗や経験を未来に活かせば、それは貴重な財産になります。エジソンだって、失敗失敗の連続だったはずです。 見えない未来を恐れても未来は変わりません。 過ぎ去った過去をいくら悔やんでも、悔やんだだけでは未来は何も変わりません。 未来は今の積み重ねです。「いま」を大切に。